空家を持っているけれど、どうやって管理すればいいのか分からない…そんな悩みを抱える人は少なくありません。
しかし、実は空家管理は、特別な資格がなくても誰でも始められます。
しっかりとポイントを押さえれば、初心者でも安全かつ効率的に管理が可能です。
この記事では、空家管理を自分で行うための方法やチェック項目、頻度、注意点などを分かりやすく解説していきます。
空家管理を自分でするのは本当に可能?初心者でもできる理由とは
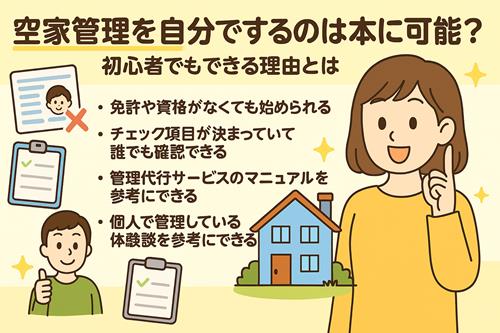
空家管理はプロだけができるものではありません。
正しい知識と道具を使えば、誰でも実践できます。
特別な資格や免許がなくても始められるから
空家管理に資格は必要ありません。
建築士や管理業者のような専門知識がなくても、基本的な作業は一般の人でも対応できます。
実際に総務省の「住宅・土地統計調査」によると、全国で約849万戸の空家があり、多くの所有者が自分で管理を行っています。
このように、空家管理は制度的にも法律的にも、個人が実施することが認められているのです。
チェック項目が決まっていて誰でも確認できるから
空家の点検は、決まったチェックリストに沿って行うことで誰でも実施可能です。
玄関や窓の施錠確認、カビの有無、水道や電気の異常チェックなど、内容はシンプルです。
あらかじめチェックリストを作成しておけば、漏れなく点検できます。
東京都では「空家管理の手引き」も公開しており、チェック内容の参考になります。
管理代行サービスのマニュアルを参考にできるから
空家管理を代行する業者の多くは、チェック内容を公開したり、利用者向けにマニュアルを配布しています。
それらを活用すれば、プロがどんな点を見ているのかを学びながら、自分でも同じように管理ができます。
例えば、空家管理サービス「カリアゲJAPAN」では、管理代行の内容を細かく紹介しています。
参考:カリアゲJAPAN
実際に個人で管理している人の体験談を多く参考にできるから
最近では、空家管理に関する個人の体験談をブログやYouTubeで紹介する人も増えています。
そういった情報を参考にすることで、自分が行う際の不安を減らすことができます。
動画では作業の様子がリアルに分かるので、初心者にとって特に参考になります。
空家管理を自分でする前に知っておきたい基礎知識

空家管理には法律的な知識や、トラブルを防ぐための基礎情報が必要です。
空家管理の法律上の義務を理解する
空家の所有者は、適切に管理する責任があります。
これは民法だけでなく、行政の指導対象にもなることがあります。
特に、倒壊やごみの不法投棄などによって近隣に迷惑がかかると、改善命令が出ることもあります。
参考:国土交通省 空家等対策
空家等対策特別措置法の内容を知っておく
この法律は、空家が「特定空家」と判断された場合に、自治体が是正命令を出せることを定めたものです。
命令に従わないと、罰則や強制執行もあり得ます。
また、空家が「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置も打ち切られる可能性があります。
空家の放置がもたらすリスクを理解する
放置された空家は、火災・倒壊・犯罪の温床になるリスクがあります。
空家の放置は、資産価値を下げるだけでなく、近隣への悪影響も大きいのです。
特に空き巣や不法侵入が発生しやすくなるため、治安の悪化にもつながります。
近隣トラブルや行政指導の可能性があることを知る
草木が繁茂して道路にはみ出したり、害虫が発生したりすると、近所の人とのトラブルになります。
そうなると、自治体から行政指導が入る可能性もあります。
定期的な清掃と見回りをすることで、近隣との良好な関係を保つことができます。
空家管理を自分でするときの準備と必要な道具

安全に空家を管理するには、適切な道具と服装が必要です。
軍手・長靴・懐中電灯など安全装備を用意
空家の中は暗く、ほこりやゴミが多いこともあります。
軍手や長靴、懐中電灯は必須です。
安全のためヘルメットもあると安心です。
また、屋根裏や床下を点検する際には、ヘッドライトが便利です。
草刈り機や剪定ばさみなど庭の手入れ道具を準備
庭や敷地内の雑草や木の枝を放置すると、害虫の温床になります。
定期的に草刈りや剪定をすることで、見た目の印象も良くなります。
音が出る作業は、近隣住民への配慮も忘れずに行いましょう。
カビや雨漏り確認用の除湿器・湿度計を用意する
空家は使われていないため、湿気がこもりやすく、カビが発生しやすいです。
除湿器や湿度計を置いておくと、環境を安定させることができます。
また、雨漏りがある場合は早めに修繕が必要です。
点検記録を残すためのチェックシートを用意
管理のたびにチェック内容を記録することで、異常の早期発見につながります。
記録は紙だけでなく、スマホで写真付きメモを残すのも有効です。
家族や他の管理者と共有できるように、クラウドを活用するのもおすすめです。
空家管理を自分でするときのチェックポイント一覧

空家管理で見るべきポイントは複数ありますが、以下の項目を定期的に確認すれば、問題の早期発見につながります。
郵便受けに郵便物が溜まっていないか
郵便物が溜まっていると、「この家は誰もいない」と思われてしまいます。
空き巣や不法侵入のリスクを高める要因にもなるため、訪問時には必ず郵便受けをチェックしましょう。
ポストに「転送不要」と書かれた郵便物が残っていた場合は、転送手続きを行うか、定期的に回収する必要があります。
日本郵便の「転居届」サービスを使えば、郵便物を新住所に転送できます。参考:日本郵便 転居届
玄関や窓がしっかり施錠されているか
空家は犯罪のターゲットになりやすいため、鍵の閉め忘れには特に注意が必要です。
玄関だけでなく、勝手口やトイレの小窓なども確認しましょう。
また、鍵穴の異常や破損がないかも併せて点検することが大切です。
防犯強化のためにはセンサーライトや防犯カメラの設置もおすすめです。
室内にカビや湿気がないか
使用されていない家は通気が悪く、湿気が溜まりやすい環境になります。
押し入れや浴室など、特に湿気がこもる場所を重点的に確認しましょう。
窓を開けて換気を行うだけでも湿気の蓄積を防げます。
除湿剤を置いておくのも効果的です。
日本気象協会のサイトでは、湿度管理に関する情報も紹介されています。
水道・ガス・電気の異常がないか
水道が錆びついていたり、ガスが漏れていたりする可能性もあります。
使わない期間が長い場合は元栓を閉めることも検討しましょう。
使用時には、水の濁りや異臭、ガスの臭いがないか確認し、電気のブレーカーも正常かを点検します。
異常がある場合は、自治体指定の専門業者に相談するのが安心です。
庭や敷地内に雑草やゴミが溜まっていないか
雑草が生い茂ると、見た目が悪くなるだけでなく、害虫の発生源にもなります。
また、敷地が荒れていると不法投棄を誘発する恐れもあります。
定期的に草刈りを行い、清潔な状態を保つよう心がけましょう。
清掃作業時は、地域のルールに従ってゴミを分別・処分する必要があります。
外壁や屋根にひび割れや破損がないか
外壁や屋根に傷みがあると、雨漏りやカビの原因になります。
特に梅雨や台風の時期には、早めに修繕することが重要です。
小さなヒビでも早めに補修すれば、大きな工事を防ぐことができます。
ドローン点検サービスなどを活用すれば、安全に屋根のチェックも可能です。
動物の侵入や害虫の発生がないか
ネズミやハクビシン、シロアリなどが侵入すると、建物に深刻な被害を与えます。
天井裏や床下から音がする、異臭がする場合は、すぐに調査が必要です。
侵入を防ぐには、通気口や換気扇などの開口部にネットを張るなどの対策が効果的です。
害虫駆除は専門業者に依頼するのが安全です。
空家管理を自分でする際のおすすめチェック頻度とは

空家の状態を良好に保つためには、点検の頻度も非常に重要です。
最低でも月1回の訪問が理想
定期的に確認することで、小さな異常にも早く気づくことができます。
月1回の訪問を目安にして、点検のたびに記録を残すことをおすすめします。
訪問が難しい場合は、誰かに代わりに行ってもらう方法も考えておきましょう。
梅雨や台風の前後は追加で点検が必要
梅雨時はカビ、台風時は雨漏りや外壁の破損リスクが高まります。
気象状況に応じて、柔軟に訪問頻度を増やすのが理想です。
特に強風や大雨のあとは、屋根や排水溝の状態を重点的に確認しましょう。
国土交通省の気象防災サイトでは、災害前後の注意点も紹介されています。
参考:国土交通省 災害情報
冬場は凍結防止のためにこまめな確認が重要
寒冷地では、水道管の凍結や破裂が多く発生します。
凍結防止ヒーターの設置や、水抜きを行うことでトラブルを防げます。
冬季は少なくとも2〜3週に1回程度の点検を推奨します。
長期不在時はご近所や知人に一時的な見回りを依頼するのも有効
長期間自分で訪問できない場合は、信頼できる人に定期的な見回りをお願いしましょう。
その際は、チェックポイントを書いたリストを渡すとスムーズです。
近隣住民との関係を良好に保つことが、空家管理の大きな支えになります。
空家管理を自分でするメリットとデメリット

自分で管理することで得られるメリットは多いですが、デメリットも理解しておくことが大切です。
コストを大幅に節約できるのがメリット
空家管理を業者に委託すると、月に数千〜数万円の費用がかかります。
自分で行えば、それらのコストをほぼゼロに抑えることができます。
道具を一度揃えれば、継続的な支出も少なくて済みます。
自分の目で状態を確認できる安心感がある
業者に任せるよりも、自分で管理することで細かな状態に気づきやすくなります。
写真や動画で確認するだけでは分からない部分も、自分の目で見ることで安心感が得られます。
時間や移動の手間がかかるのがデメリット
遠方にある空家の場合、移動の時間と費用が負担になります。
また、日中に時間を取るのが難しい人にとっては、定期的な訪問が困難になることもあります。
管理の知識がないと見落としが起きやすい
専門的な知識がないと、小さな異常を見逃してしまうことがあります。
そのため、チェックリストや体験談、信頼できるサイトを活用して知識を補うことが大切です。
空家管理を自分でする場合の注意点とリスク対策

空家管理を自分で行う際は、安全性やリスクへの対処がとても重要です。
以下の注意点を押さえておきましょう。
安全確保のため単独での作業を避ける
空家での作業は、倒壊や転倒、害虫被害などの危険があります。
なるべく家族や友人と複数人で行動するようにしましょう。
特に屋根の上や高所作業などは、単独作業は避けてください。
やむを得ず一人で作業する場合は、家族や知人に訪問先と終了時間を必ず伝えておきましょう。
害虫・害獣の発生に備えて防除対策を取る
空家はネズミ、シロアリ、蜂などが住み着きやすい環境です。
市販の忌避剤や捕獲器を活用し、定期的に清掃することで発生を防ぎましょう。
侵入される前に通気口や床下の穴をふさぐ予防策も大切です。
もし大量発生してしまった場合は、早めに専門の害獣駆除業者に依頼することをおすすめします。
火災や漏水リスクに備えて保険に加入する
空家は誰も住んでいないため、火災や漏水が起きたときに発見が遅れがちです。
「空家専用の火災保険」や「家財のない建物のみの保険」などもあります。
火災や自然災害に備えるため、必要最低限の保険に入っておくと安心です。
損害保険協会の情報も参考になります。日本損害保険協会
管理状況を記録し万一に備える
点検や清掃のたびに、作業内容や日付を記録しておくことが重要です。
万が一、近隣トラブルや行政からの指摘があった場合に、管理実績を示す証拠になります。
紙のノートでも良いですが、スマホアプリやクラウドで記録するのも便利です。
写真を添えて保存すると、より正確な管理履歴になります。
空家管理を自分でするのが難しいと感じたときの対処法

どうしても自分での管理が難しい場合は、無理せずプロの手を借りる選択肢もあります。
地域の空家管理サービスを利用する
多くの自治体では、地元の企業と提携して空家管理サービスを提供しています。
料金も手頃で、空家の所在自治体での管理が可能なので安心です。
市役所や町役場に相談すれば、サービス内容や利用方法を教えてくれます。
「アキカツ」「カリアゲJAPAN」などの空家専門サービスを検討する
「アキカツ」や「カリアゲJAPAN」は、全国対応の空家専門サービスです。
月額数千円から利用でき、建物の状態をプロが定期的にチェックしてくれます。
写真付き報告書を提出してくれるため、遠方に住んでいる方でも安心して任せることができます。
近隣住民や親族に定期的な見回りをお願いする
信頼できる人が近くにいるなら、負担の少ない範囲で見回りをお願いする方法もあります。
あらかじめチェックポイントや訪問頻度を相談し、協力してもらいましょう。
お礼としてちょっとした贈り物や交通費を渡すと、今後も継続的に協力してもらいやすくなります。
最低限の管理だけを自分で行い、専門業者に一部委託する
全部を自分でやる必要はありません。
たとえば室内の換気や郵便物の確認は自分で、草刈りや害虫駆除は業者に依頼するなど、分担する方法も有効です。
費用を抑えながら、無理のない形で空家の状態を良好に保つことができます。
まとめ|空家管理を自分でするために必要なポイントと頻度を理解しよう

空家管理は、専門知識がなくてもポイントを押さえれば自分で行うことができます。
特に大事なのは、「定期的にチェックすること」「安全と記録を重視すること」「必要に応じて専門家を頼ること」です。
最低でも月1回の訪問と、季節や災害のリスクを意識した追加点検を心がけましょう。
管理が難しい場合は、地域サービスや専門業者を活用することで、無理なく続けることができます。
この記事を参考に、空家を安全かつ快適に保つための第一歩を踏み出してください。


