空き家が全国的に増加し、老朽化による倒壊事故が多発しています。
実際に通行人がけがをしたり、隣の家に被害が及ぶなど、社会問題に発展しています。
この記事では、なぜ空き家の倒壊が増えているのか、その背景とともに、所有者が負うべき法的責任や、事故を防ぐための管理方法、行政の支援制度などを詳しく解説します。
放置された空き家が引き起こすリスクや責任を正しく理解し、事故を未然に防ぐための知識を身につけましょう。
空き家の倒壊事故がなぜ増えているのか?
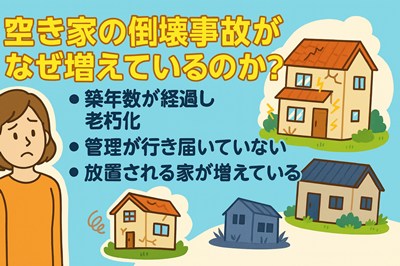
近年、空き家の倒壊事故が増加していますが、その背景には複数の要因が存在します。
ここでは代表的な3つの原因を紹介します。
築年数が経過し老朽化が進んでいる
建物は時間とともに劣化します。
特に空き家は人が住んでいないため換気や掃除がされず、湿気や害虫によって建材が傷みやすくなります。
築30年以上の家屋は、屋根や柱、外壁などに重大な損傷が見られるケースも多く、倒壊リスクが高まります。
国土交通省の「空き家実態調査」でも、築年数の古い木造住宅が特に危険とされており、早めの対応が求められます。
所有者が遠方に住んでいて管理が行き届いていない
相続した空き家が地元から離れた場所にあると、定期的な管理が難しくなります。
特に高齢の親族からの相続物件ではこの傾向が顕著です。
年に数回しか訪れない場合、屋根の破損や基礎のひび割れなど、小さな劣化を見逃しがちです。
その結果、気づかないうちに建物が傾き、強風や地震で突然倒壊することもあります。
遠方にある空き家のリスクを正しく認識し、管理の方法を検討する必要があります。
人口減少や過疎化で放置される空き家が増えている
日本全体で人口が減少しており、特に地方では若者が都市部へ流出しています。
これにより、空き家の再利用が進まず、放置されるケースが増えています。
総務省の統計によると、2023年時点で全国の空き家数は約890万戸と過去最多を記録しています。
過疎地域では空き家を活用するニーズが低く、取り壊す費用もかけられず、放置されがちです。
空き家が倒壊するとどんな事故につながる?

倒壊した空き家はさまざまな事故の原因となり、周囲に深刻な被害をもたらす可能性があります。
通行人や近隣住民がけがをする可能性
空き家が崩れることで、通行中の人に屋根瓦や壁の一部が落下し、けがをするケースがあります。
過去には子どもが倒壊した塀の下敷きになった事例もあり、命に関わる危険性があります。
人的被害が出ると、所有者には損害賠償責任が問われることになります。
自治体によっては空き家の安全確認を促すパンフレットを配布しており、注意喚起がされています。
隣接する建物や車に被害を与える可能性
倒壊により隣の家の壁や屋根を破損したり、停車中の車両に被害を与えることもあります。
このような物損事故が起こると、修繕費や代替費用を賠償しなければなりません。
保険に入っていない場合はすべて自己負担となる可能性があります。
火災の延焼リスクが高くなる
空き家には枯れ草やゴミが溜まりやすく、火がつきやすい環境になっています。
放火の標的にもなりやすいです。
特に木造家屋の場合、近隣住宅へ火が燃え移る危険があります。
一度火災が起これば大規模な被害になることも多く、消防や自治体も懸念しています。
地域の景観や安全に悪影響を及ぼす
倒壊した空き家が放置されると、景観が悪化し、治安の悪化やゴミの不法投棄などの温床になります。
地域住民の生活環境にも悪影響を与えることになり、まち全体の価値が下がる恐れもあります。
こうした社会的損失は、単なる個人の問題ではなく、地域全体の課題となっています。
空き家の倒壊事故で所有者に発生する責任
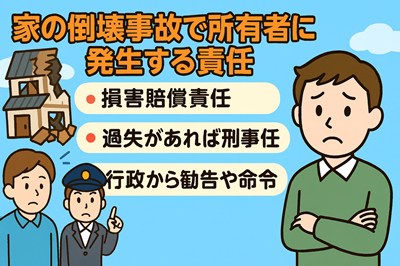
空き家が倒壊した場合、所有者は法的に大きな責任を負うことになります。
ここでは代表的な3つの責任について解説します。
民法に基づく損害賠償責任を問われる
民法717条では、建物の設置や保存に瑕疵(欠陥)がある場合、その所有者が損害を賠償する責任があると定められています。
倒壊により他人に損害を与えた場合、所有者は賠償責任を免れません。
過失があれば刑事責任に問われる
事故によってけが人や死者が出た場合、過失致死傷罪など刑事責任に問われる可能性があります。
空き家の管理を怠ったことが「過失」と判断されれば、罰金や懲役刑の対象になることもあります。
これは重大な結果を招く可能性があるため、所有者は十分に注意しなければなりません。
特定空家に指定されると行政から勧告や命令が出される
「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、倒壊の恐れがある空き家は「特定空家」として行政から勧告・命令を受けることがあります。
命令に従わない場合、行政代執行(強制解体)が行われ、費用は所有者に請求されます。
法的強制力をもって空き家の管理責任を果たさせる仕組みとなっています。
空き家の倒壊事故を防ぐために必要な管理と対策

空き家の倒壊事故を未然に防ぐには、定期的な管理と対策が欠かせません。
以下のような方法を取り入れることで、安全性を高めることができます。
定期的に建物の状態を点検・修繕する
建物の外壁や屋根、基礎部分を定期的に確認し、破損や劣化があれば早めに修繕することが重要です。
特に雨漏りやシロアリ被害は、放置すると倒壊につながる危険な要因です。
プロの建築士や工務店に点検を依頼することで、問題点を早期に発見しやすくなります。
年に1〜2回の点検を習慣にすることが推奨されています。
庭や外構を整えて周囲に危険がないようにする
建物だけでなく、庭や塀、門など外構部分の管理も重要です。
特にブロック塀は老朽化により倒壊する恐れがあります。
草木が伸び放題になると、害虫の発生や放火のリスクも高まります。
近隣住民の安全と良好な景観を保つためにも、定期的な清掃と整備を行いましょう。
塀の点検方法などについては、国土交通省|ブロック塀の安全点検マニュアルを参考にしてください。
信頼できる管理代行サービスを利用する
遠方に住んでいて管理が難しい場合は、空き家管理サービスを利用するのも有効です。
管理会社が定期的に訪問して建物の状態をチェックし、報告してくれるため、安心感があります。
月額5,000円程度から利用可能なサービスもあり、費用対効果が高いのが特徴です。
自治体によっては管理代行業者の一覧を提供していることもあるため、確認してみましょう。
空き家の倒壊事故を防ぐために知っておきたい法律

空き家に関する法律や制度を知っておくことで、適切な対応がしやすくなります。
ここでは代表的な法律を紹介します。
空家等対策の推進に関する特別措置法
2015年に施行されたこの法律は、自治体が空き家の実態を把握し、必要に応じて勧告・命令・行政代執行を行えるようにするものです。
倒壊や衛生面で問題のある空き家は「特定空家」に指定され、所有者に対して管理や解体を促す措置が取られます。
この法律は、空き家問題を放置できない社会的課題として扱う根拠となっています。
詳しくは国土交通省 空家等対策特措法をご覧ください。
特定空家に指定される基準と行政の対応
以下のような状態の空き家が、特定空家と認定されることがあります
・倒壊の危険がある
・衛生上有害(悪臭、害虫の発生)
・景観を著しく損なっている
認定されると、助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行という流れで措置が講じられます。
命令に従わない場合、最大50万円の過料が科される可能性もあります。
所有者責任に関わる民法や地方自治体の条例
民法第717条のほか、地方自治体ごとに空き家条例を制定しているケースもあります。
たとえば、東京都足立区や愛知県豊橋市では、空き家管理に関する詳細なルールが設けられています。
地域によってルールが異なるため、必ずお住まいの自治体の公式サイトを確認しましょう。
空き家が倒壊事故を起こした場合の保険や補償の仕組み

空き家が倒壊してしまった場合に備えて、保険の内容を理解し、適切に加入しておくことが重要です。
火災保険や地震保険の補償内容を確認
火災保険や地震保険は建物の損壊に対する基本的な補償を提供します。
ただし、空き家として使われていない建物は契約対象外となるケースもあるため注意が必要です。
保険会社に「空き家として契約可能か」を事前に確認しておくことが大切です。
個人賠償責任保険で第三者への損害をカバーできる場合がある
倒壊によって第三者にけがや損害を与えた場合、個人賠償責任保険でカバーできることがあります。
自動車保険や火災保険に付帯している場合もあるので、保険証券を見直してみましょう。
思わぬ出費を防ぐためにも、保険の見直しは定期的に行うことが重要です。
保険適用外の損害には自己負担が発生する可能性がある
管理不足による倒壊は「保険金の対象外」とされることがあります。
たとえば、「明らかに修繕を怠っていた」と判断された場合は補償されない可能性が高いです。
事故が起こる前に適切な保守管理を行っていることが保険の適用条件にもなります。
空き家の倒壊事故に備えるための行政支援や相談窓口
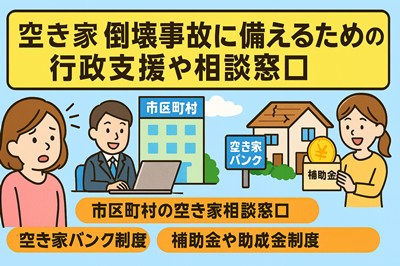
空き家問題には各自治体も積極的に対応しており、支援策や相談窓口が用意されています。
市区町村の空き家相談窓口を活用する
多くの市町村では「空き家相談窓口」を設置しており、管理方法や補助金の申請について相談できます。
相談は無料で受けられることが多く、専門家によるアドバイスがもらえる貴重な機会です。
お住まいの自治体の公式サイトや窓口に問い合わせてみましょう。
空き家バンク制度を利用して利活用を検討する
空き家バンクとは、空き家を売りたい・貸したい人と、借りたい・買いたい人をつなぐ制度です。
地域活性化や移住促進の一環として多くの自治体が導入しています。
空き家を活用することで、倒壊リスクも大きく減らすことが可能です。
補助金や助成金制度で修繕・解体の費用負担を軽減できる
自治体によっては空き家の修繕や解体にかかる費用の一部を補助してくれる制度があります。
条件を満たせば、数十万円の補助金が支給されることもあります。
申請時期や必要書類に注意し、余裕を持って準備しましょう。
空き家の倒壊事故を防ぐためにリフォームや解体は有効?

老朽化が進んだ空き家に対しては、リフォームや解体といった抜本的な対策も視野に入れるべきです。
ここでは、それぞれのメリットと注意点を解説します。
老朽化が進んでいる場合は解体が安全性確保に有効
すでに傾いていたり、大きな損傷がある場合は、修繕よりも解体の方が合理的です。
倒壊する前に解体しておくことで、第三者への被害や法的責任を回避できます。
また、空き地として再利用する選択肢も広がります。更地にして売却することで、維持費を削減できるのも大きな利点です。
解体費用は建物の構造や広さによって異なりますが、木造住宅であれば30〜80万円ほどが一般的です。
リフォームにより再活用や賃貸などの選択肢が広がる
建物がまだ使用できる状態であれば、リフォームによって再活用する方法もあります。
たとえば、民泊やシェアハウス、地域交流施設として生まれ変わるケースも増えています。
空き家を資産として生かすことで、放置リスクも減り、地域にも貢献できます。
リフォーム費用は内容によって大きく異なるため、複数業者に見積もりを取ることが重要です。
市町村によっては解体やリフォームに補助金が出る
多くの自治体が、空き家対策の一環として解体費やリフォーム費への補助金制度を設けています。
補助率は工事費の1/2〜2/3、上限額は30〜100万円程度が一般的です。
例えば、長野県松本市では、老朽空き家の解体費に最大100万円の補助があります。
制度の詳細や条件は自治体によって異なるため、公式サイトや相談窓口で事前確認を行いましょう。
まとめ|空き家の倒壊事故に関する法律・責任・対策を正しく理解しよう
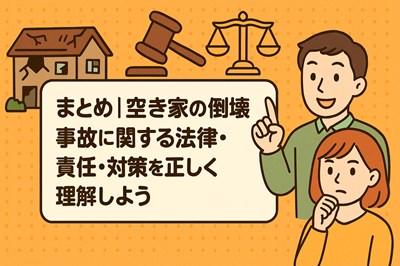
空き家の倒壊は、けがや火災、景観悪化などさまざまな社会的問題を引き起こします。
所有者としての責任を自覚し、事故を未然に防ぐ対策が必要です。
事故を未然に防ぐには日頃の管理と情報収集が大切
定期的な点検・清掃、修繕を行うことが倒壊防止の第一歩です。
遠方に住んでいる場合は管理代行サービスや地元の親族に協力を依頼するのも効果的です。
さらに、行政の支援策や保険制度など、正しい知識を身につけることでリスクを減らせます。
法的責任や行政の対応について早めに把握しておくべき
民法、空家特措法、各自治体の条例など、所有者が知っておくべき法律は多岐にわたります。
事故が起きてからでは遅いため、早めに調査・相談を行うことが肝心です。
まずは自治体の空き家相談窓口を活用し、現状を把握しましょう。
活用・売却・解体など自分に合った対策を検討しよう
空き家は管理するだけでなく、「活用」することで価値を見出せます。
売却や賃貸、地域施設としての利活用など、専門家と相談しながら最適な方法を見つけましょう。
放置せず、前向きに動くことが、将来の安心と地域の安全につながります。


